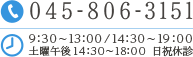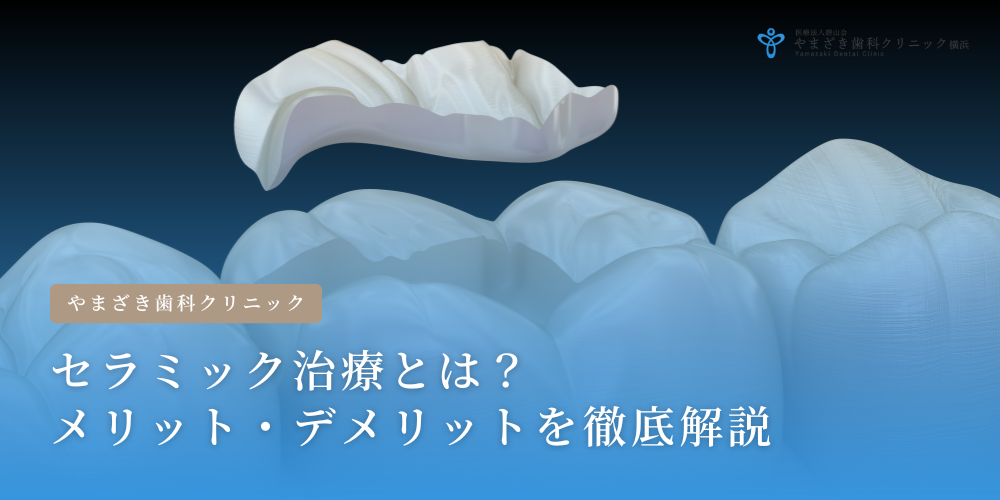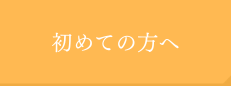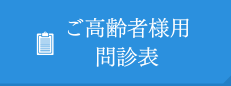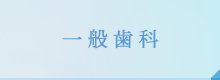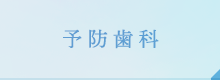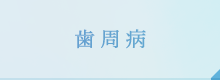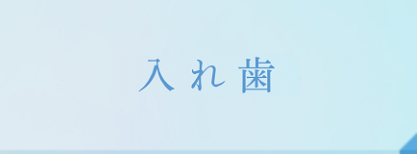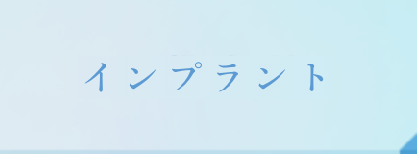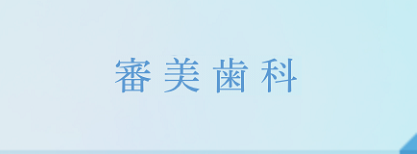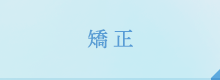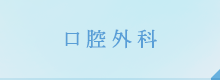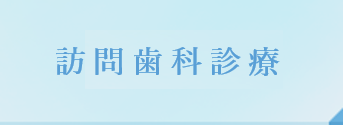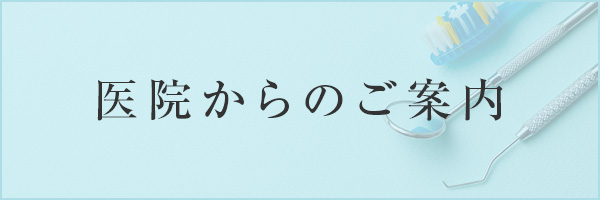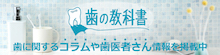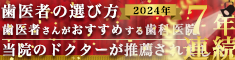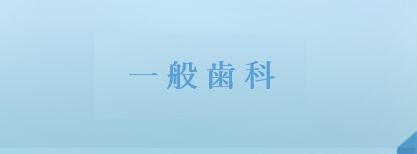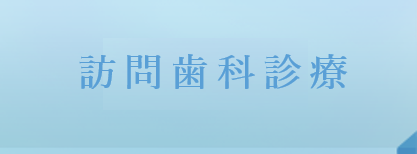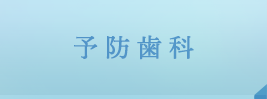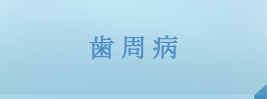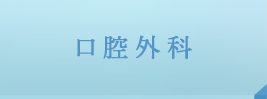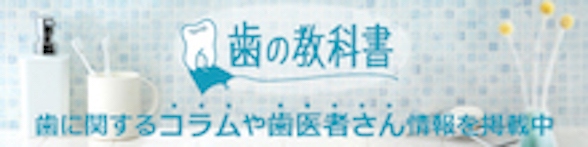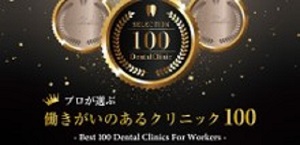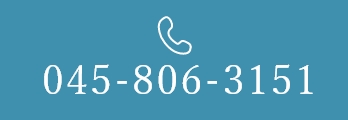セラミック治療のメリットとは?銀歯との違いと注意点も解説
2025.05.03更新

目次
やまざき歯科クリニックです。
「銀歯の見た目が気になる」「白くて自然な歯にしたい」と感じたことはありませんか。
保険診療ではできない美しさと機能性を両立できる方法として、セラミック治療が注目されています。
セラミック治療は歯科材料として高い審美性と生体親和性が評価されており、多くの歯科医師も推奨しています。
今回はセラミックのメリットを中心に、治療の特徴や注意点をわかりやすく解説します。
見た目の美しさだけでなく、虫歯予防や金属アレルギー対策などの利点も理解できる内容です。
結論として、セラミック治療は審美性と健康の両面で非常に優れた選択肢です。
セラミック治療とは何か
セラミック治療とは、虫歯や欠損した歯の部分を修復するためにセラミック素材の詰め物や被せ物を使う自由診療の方法です。
従来の銀歯とは異なり、天然の歯に近い色味や透明感を再現できるのが特徴です。
また、口腔内での変形や変色が少なく、長期間の使用にも耐えやすい点が評価されています。
治療は詰め物(インレー)や被せ物(クラウン)、さらには前歯の見た目を整えるラミネートベニアなど多様に対応可能です。
機能性と美しさを両立させたい方にとって、セラミックは非常に魅力的な治療法といえるでしょう。
セラミックの主なメリット
セラミック治療には複数の明確な利点があります。
代表的なものは、見た目の自然さ、耐久性、金属アレルギーの回避、二次虫歯のリスク低減などです。
特に審美性の高さは、前歯など目立つ部分の治療で大きな効果を発揮します。
- ・白く美しい仕上がりで天然歯に近い
- ・表面が滑らかで汚れが付きにくく清潔
- ・金属不使用で金属アレルギーのリスクなし
- ・歯と強力に接着するため外れにくい
- ・経年劣化が少なく長く使える
これらの特徴は、見た目だけでなく機能面でも優れた治療効果をもたらします。
セラミックと銀歯の違い
保険診療で使われる銀歯とセラミックでは、見た目や耐久性に大きな違いがあります。
銀歯は金属のため、時間とともに変形や腐食を起こす可能性があります。
一方で、セラミックは変色しにくく、接着性に優れているため虫歯の再発リスクも抑えられます。
費用面ではセラミックが高額ですが、その分長期的に見れば再治療のリスクも少なく経済的ともいえます。
美しさを重視する方にとっては、セラミックが優れた選択肢となるでしょう。
セラミックのデメリットと注意点
どんな治療にも短所はあり、セラミックも例外ではありません。
まず、自由診療であるため費用が高くなります。1本あたりの相場は数万円から十数万円程度です。
また、強度が高い反面、過度な力がかかると割れることがあるため、歯ぎしりがある方は注意が必要です。
さらに、厚みを確保するため歯を多く削る必要があり、健康な歯質を失う場合もあります。
メンテナンスを怠ると、せっかくのセラミックもトラブルの原因になるため定期的な検診が欠かせません。
セラミックを長く使うためのポイント
セラミックを長持ちさせるには、適切なケアとメンテナンスが重要です。
普段からのブラッシングやフロスの使用はもちろん、定期的な歯科検診も欠かさないようにしましょう。
特に歯ぎしりがある方は、ナイトガードの使用が推奨されます。
- ・毎日の丁寧なブラッシングとデンタルフロスの使用
- ・硬いものを避けるなど食生活に配慮する
- ・歯ぎしり対策としてナイトガードを利用する
- ・半年に1回は歯科医院での定期検診を受ける
正しく使えば、セラミックは10年、20年と長く快適に使用することができます。
まとめ
セラミック治療は、審美性や耐久性に優れた治療法であり、多くの患者にとって魅力的な選択肢です。
金属アレルギーの心配がなく、長期間美しさを保てる点は大きなメリットです。
一方で、費用や割れやすさなどの注意点もありますが、適切なケアをすればその恩恵は十分に得られます。
見た目と機能性を両立したい方には、セラミック治療の導入をおすすめします。
少しでも参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
横浜市泉区立場駅から徒歩3分の歯医者・歯科
『やまざき歯科クリニック』
住所:横浜市泉区和泉中央南1−3−4 GROW YOKOHAMA TATEBA 1F
TEL:045-806-3151
投稿者: